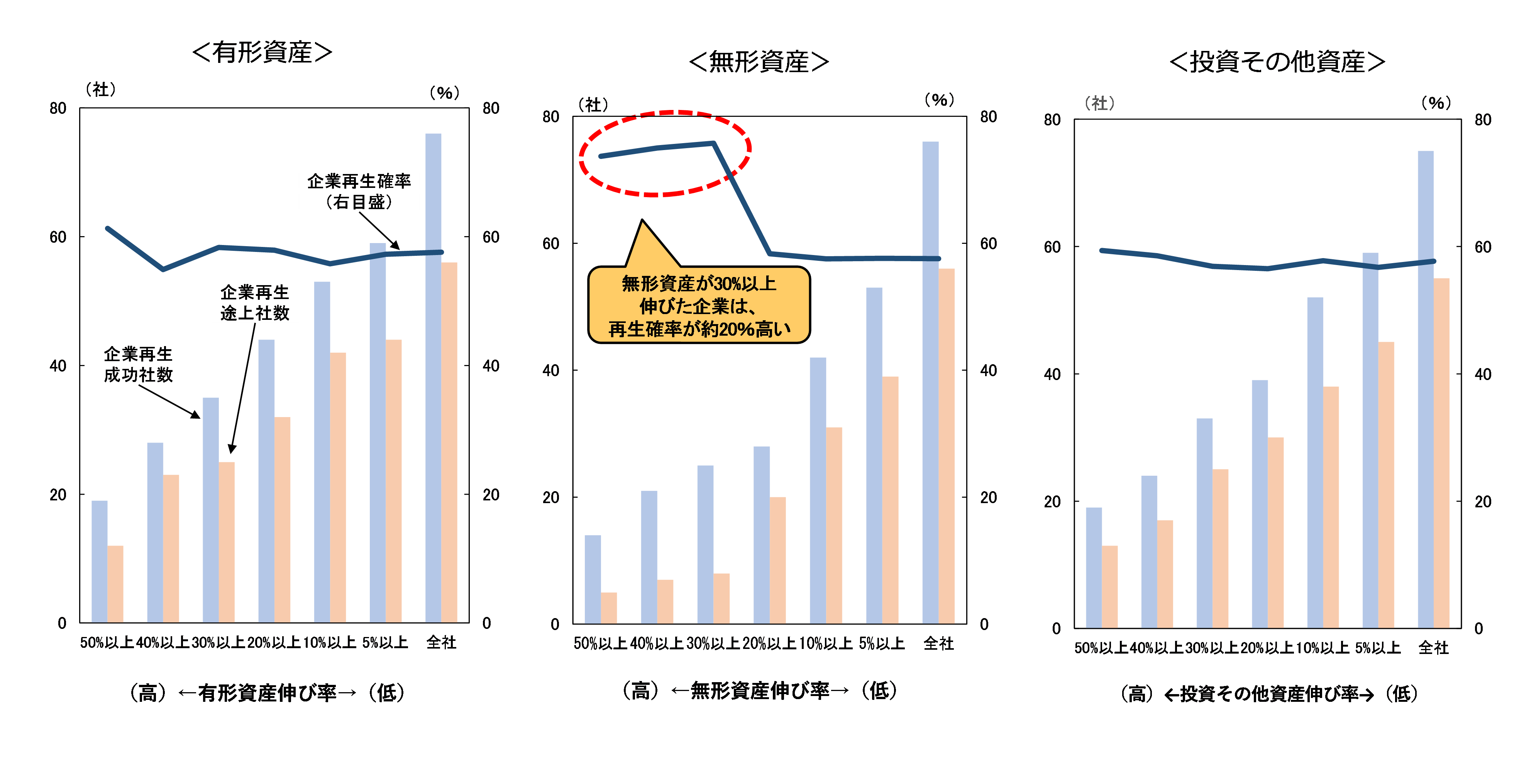30年ぶりのチリ訪問で見つけた「忘れ物」
=もう一つの「9.11」の知られざる現実=
「思ったより汚いな」-。この秋、30年ぶりに降り立った南米チリの首都サンティアゴは、埃(ほこり)とゴミが舞い上がる、落書きだらけの街に一変していた。長年、自分が恋い焦がれてきたものが汚されたような軽い失望感を抱いてしまった。
チリ? サンティアゴ? 多くの方はなじみのない場所だろう。地球の裏側(チリにとっては日本が裏側だが...)、南北に異常に細長い国-。こうしたイメージが大半なのではないだろうか。東京からサンティアゴまで約1.7万キロメートル、飛行機を乗り継いで丸1日以上かかる"最果ての地"だ。
 人口515万人を擁する南米屈指の大都市サンティアゴ
人口515万人を擁する南米屈指の大都市サンティアゴ
市街からは山頂に雪を頂くアンデスの山並みを望むことができる
だが、貿易での結び付きは思いのほか強い。日本のワインの輸入量は、2015年にチリ産がフランス産を抜いてナンバーワン。サケの輸出大国としても知られるが、1970年代に現在の独立行政法人国際協力機構(JICA)が養殖技術をもたらしたものだ。北部には銅の一大産地が広がり、電気自動車(EV)の電池などに使用されるリチウムの産出国としても注目されている。
旅の動機は、青臭い言い方になるが、「青春の忘れ物」探しである。1986年末から1987年初頭にかけて、当時留学していたブラジルを起点に南米を回り、サンティアゴにも計2週間ほど滞在したことがある。街のあちこちに点在する美しい公園のたたずまいや、適度に距離を取るチリ人の控えめな姿勢、細やかさに好印象を覚えた。何かと粗雑な他の南米諸国に疲れていたせいもあって、一気にチリに魅せられた。たまたま知り合ったチリ人の家庭に厄介になって多大な歓待を受けたことも、チリファンになったゆえんだ。
しかし、それらは無知ゆえの誤解が混じっていた。「9.11」といえば、誰もが2001年の米国同時多発テロを思い浮かべるだろう。ところがチリは違う。さかのぼること1973年9月11日、世界初の民主的に選ばれた社会主義政権が、軍事クーデターによって押しつぶされた。サンティアゴにあるモネダ宮殿と呼ばれる大統領府に立てこもったサルバドール・アジェンデ大統領(当時)は、戦車や狙撃隊に加え、爆撃機によるすさまじい砲撃を受けた末に、自ら命を絶つ。時は東西冷戦の真っただ中。チリへの共産主義勢力の浸透ぶりに危機感を抱いた米国の諜報機関が、裏で糸を引いていたというのが定説だ。

チリの大統領府、モネダ宮殿
爆撃で内部は炎上した、今は修復が施されてかつての惨劇をうかがうことは難しい
新たなモネダ宮殿の主(あるじ)となったアウグスト・ピノチェト大統領(同)の下、旧政権との関与を疑われた市民が逮捕状なしで手当たり次第に連行され、そのまま虐殺されたり、いまだに行方が分からなくなったりした者も数多い。判明しているだけでも、犠牲者の数は3000人を超え、拘束されたり拷問を受けたりした人の数に至っては、4万人に上っている。その残虐ぶりは、人権蹂躙(じゅうりん)のショーケースとされているほどだ。
私がチリに訪れたときは、クーデターから13年以上が経過し、ピノチェト独裁政権も末期だったものの、わずか数カ月前に大統領自身に対する暗殺未遂事件が勃発したばかり。当局による取り締まりが再び厳しさを増していた。実際、外では自動小銃を手にしたパトロール隊を頻繁に目にした。街が整然としているのも、統制国家ならではのものといえた。チリ人の奥ゆかしさは、抑圧ゆえの悲しみと憤り、諦めを押し隠した仮の姿であり、能天気な旅行者であった私は、彼らから発せられる自由への渇望を感じ取ることができなかっただけなのだ。
後にチリの政治史を学ぶ機会があり、彼らに降りかかった残酷な歴史を知ったとき、いつかサンティアゴを再訪したいという思いが芽生えた。当時の自分を重ね合わせることで、見えなかったもの感じなかったものが何なのか知りたいという淡いリベンジ心のようなものだったかもしれない。
旅程を組むに当たって最優先としたのは、「9.11」にサンティアゴにいることだった。1990年に民政移管を遂げたものの、自由から抑圧へ、希望から絶望へと多くのチリ人の運命を一変させた屈辱の日を、街や人々がどう受け止めているのか、この目で見てみたいと思ったのだ。
こうして期待に胸を膨らませて降り立ったサンティアゴだったが、冒頭のような記憶の塗り直しを早々に迫られた。セントロと呼ばれる旧市街に宿を取ったため老朽化が目に付いたのは仕方ないとしても、それ以上に荒廃ぶりが見て取れた。お世辞にも芸術的とはいえない落書きが壁という壁にぶちまけられ、ゴミが至る所に散乱していた。アンデス下しの冷涼な風が埃(ほこり)を巻き上げ、目や喉といった粘膜にまとわりついて不快感が増した。自分の中で増幅してきた「かれんな街」というイメージが裏切られていくのを感じた(サンティアゴの名誉のために申し添えると、新市街は日本の高級住宅地も及ばないほど美しい街並みが広がっている)。
 旧市街では壁のあちこちに落書きがされているのが目立つ
旧市街では壁のあちこちに落書きがされているのが目立つ
拍子抜けしたのは「9.11」当日も同じだった。街全体が喪に服しているのかと思ったが、通常と変わらぬ様子。ただ、モネダ宮殿周辺だけが厳戒態勢に包まれていた。大型犬を連れた警官が至る所に配備され、宮殿前に広がる憲法広場は鉄柵でバリケードが築かれ、立ち入りが制限された。といっても、一触即発といったピリピリしたムードではない。その証拠に警官に「反対側の通りに行きたいのだが、広場を突っ切れないのか」と尋ねたら、申し訳なさそうに「広場の端をぐるっと回ってください」とソフトな口調で返された。
広場の一角にとりわけ人が集まっている場所があった。足を運ぶとアジェンデ大統領の銅像が目に飛び込んできた。銅像の下は、手向けられた花束と行方不明者のモノクロの写真のパネルで埋まっていた。意外にも、たたずむ人々は静かだった。近くにいたチリ人に「アジェンデは国民から崇愛されているのか」と尋ねたところ、「ああ、宮殿脇の玄関にも行ってごらん。遺体が運びだされた場所なので花束があるよ」と教えてくれた。
 モネダ宮殿を望む場所に立つアジェンデ元大統領の銅像
モネダ宮殿を望む場所に立つアジェンデ元大統領の銅像
多くの花束や行方不明者のパネルが、まだ歴史が幕を閉じていないことをうかがわせる
広場に戻ると銅線でかたどった文字が配置されていた。聞けばアジェンデ大統領がクーデター当日、宮殿内でラジオ演説した最後の言葉だという。「毎年、さまざまな形で彼をしのんでいるんだ」。やせぎすのチリ人が、カメラのファインダーをのぞきながら、ぼそっとつぶやいた。
感情をのみ込んだ厳粛なセレモニー-。これが44年たったあの日の現実だった。大声を上げるわけでもなく、涙を流すわけでもない。報道ぶりも極めて控えめに感じられた。そこには、時の風化というよりは、あいまいなまましておきたいという力学が働いているように見えた。現に当日、中道左派のミチェル・バチェレ大統領は、さらなる真相究明を求めて声を上げたが、「表沙汰にするのなら過去の話をしない人が多いだろう」という政界からの反論にかき消されてしまっている。
そもそもピノチェト氏自身も大統領退任後に国外で拘束されたが、高齢などを口実についチリで裁かれることはなく、2006年に死去している。あれだけの暴力の限りを尽くした軍や警察に対する信頼度は、依然、他の南米諸国では考えられないくらい高いとされる。
現地の日本人商社マンは、「いまだに国を分断しかねない問題なので、突き詰めることにはためらいがある。まだ国民の和解は終わっていない」と解説してくれた。宿で知り合った30代のチリ人ビジネスマンも「弾圧した側、された側の両方の関係者がいる。どちらか分からないのに、普段はあまり露骨に話をすることはない」と語る。
経済界もしかり。外資系の鉱山会社の国有化政策を推し進めていたアジェンデ政権があのまま続いていたら経済破綻しただろうという見方は強い。ピノチェト政権下で採られた新自由主義的な経済政策でチリ経済は年10%前後の成長を遂げるまでに回復した。その後、落ち込んだこともあったが、周辺国と比較するとはるかに安定的で、健全な財政運営もあって「中南米の優等生」と称されたほどだ。「政治と経済は別」というのが偽らざる本音のようだ。
3週間に及んだ今回のサンティアゴ滞在中、クーデターから圧政、民政移管までの記録を収めた「記憶と人権の博物館」に何回も足を運んだ。宮殿が爆撃される様子やアジェンデ大統領の最後の演説の肉声、軍リーダーたちの会見など映像の生々しさにただただ圧倒された。拷問の様子を赤裸々に語る姿や、独裁政権に「ノー」を突きつけた国民投票の結果に喜びを爆発させる市民の姿のビデオなどを見ると、こみ上げてくるものがあった。
 「記憶と人権の博物館」の外観
「記憶と人権の博物館」の外観
二度と惨劇を繰り返さないようにとバチェレ現大統領の1期目の2010年に開館した
これらの映像を何回も眺めては、昔歩き回ったであろう場所を訪ね歩いた。寂しい通りに面した日本食レストラン、街の角にはめ込まれたかのように配置された小さな公園、豊富な食材で溢(あふ)れかえった市場...。中には記憶違いや変貌を遂げているところもあったが、擦り合わせを続けていくことで、やっと30年前の日々が頭ではなく腹の中でつながった気がした。
ただ、何よりも想定外だったのは、かつての自分を探し歩くような時間を有したことで、生意気だった当時の心の内がよみがえったことだ。若さゆえに何でもできると信じ込んでいたあのころの感情がほとばしり、正直持て余してしまった。今思い出しても赤面してしまうが、ひょっとするとこれこそが、サンティアゴに残してきた甘酸っぱい「忘れ物」だったのかもしれない。時間が経つにつれ、そんな思いを強くしている。
(写真)筆者
タグから似た記事を探す
記事タイトルとURLをコピーしました!